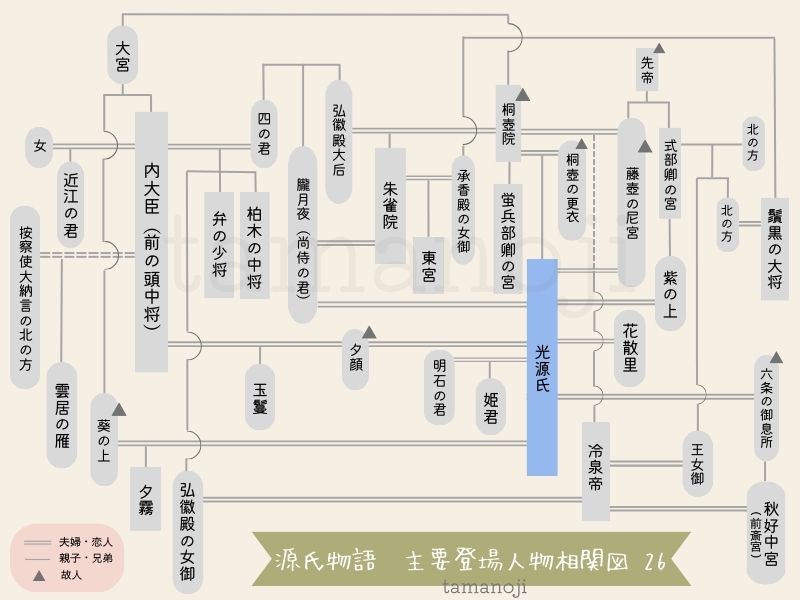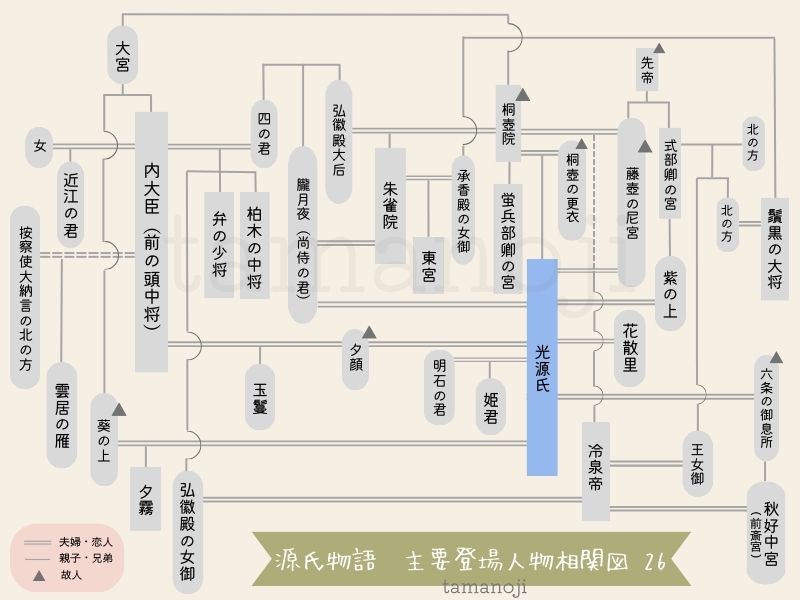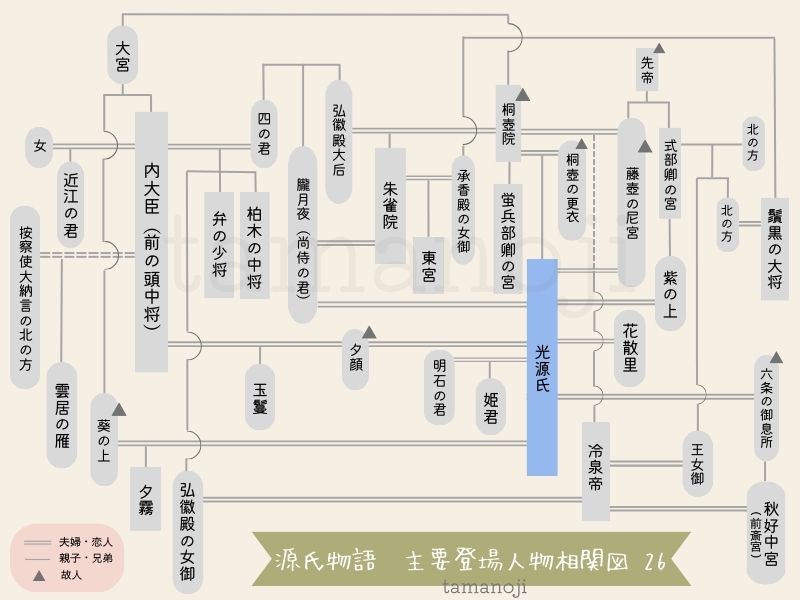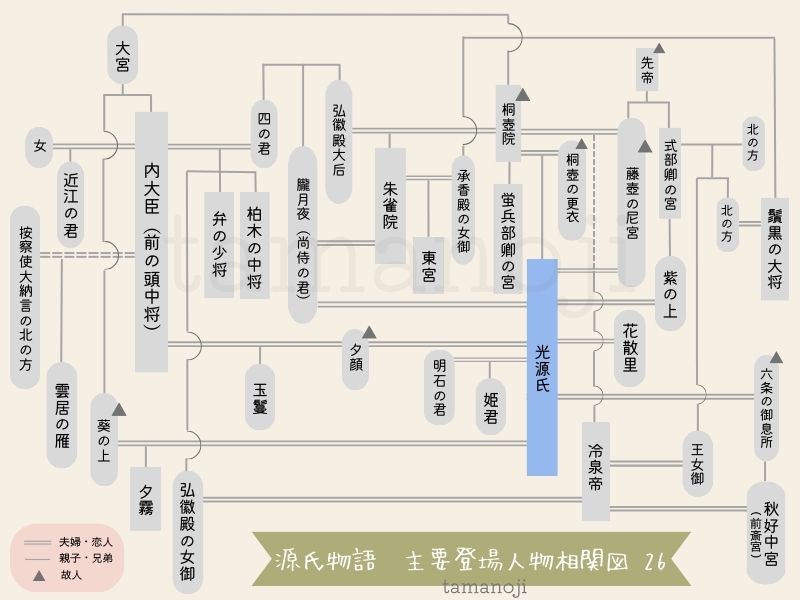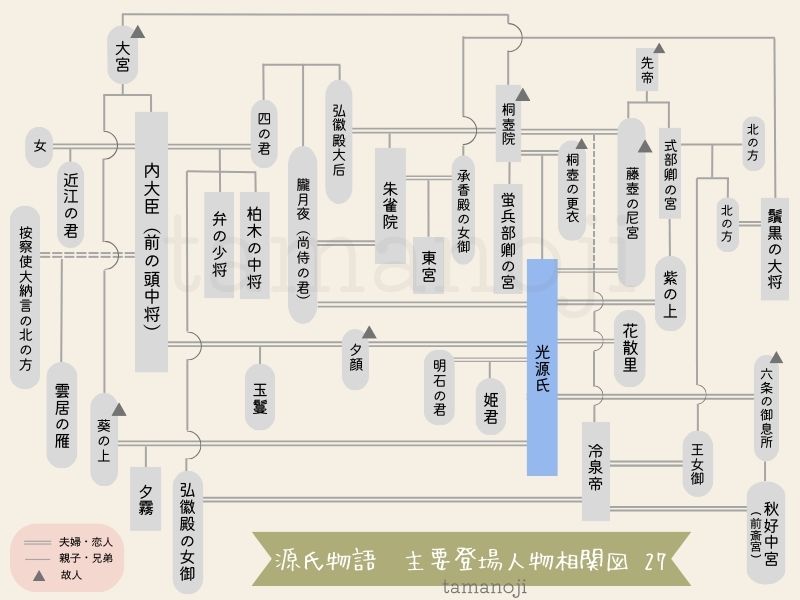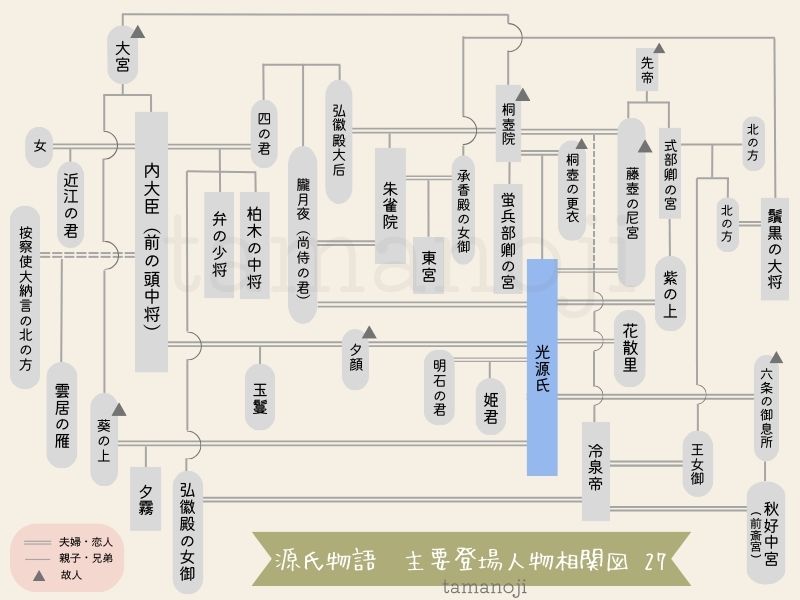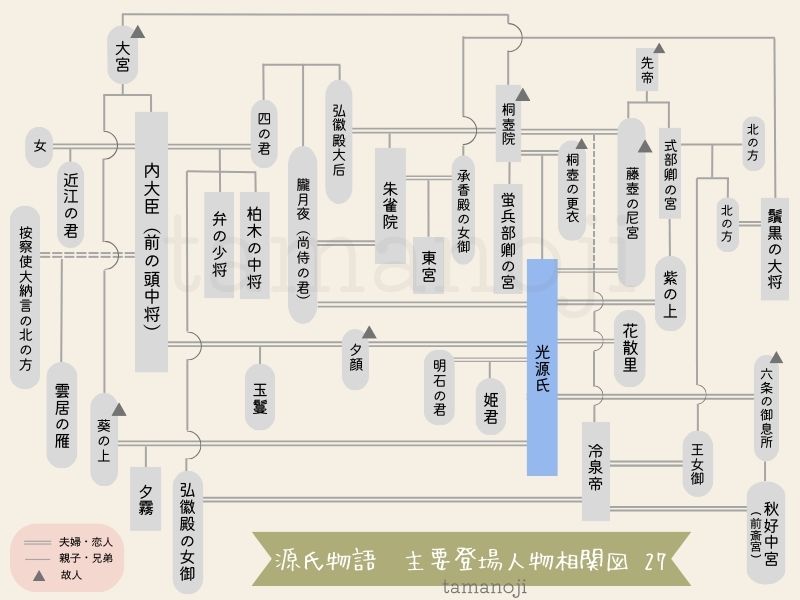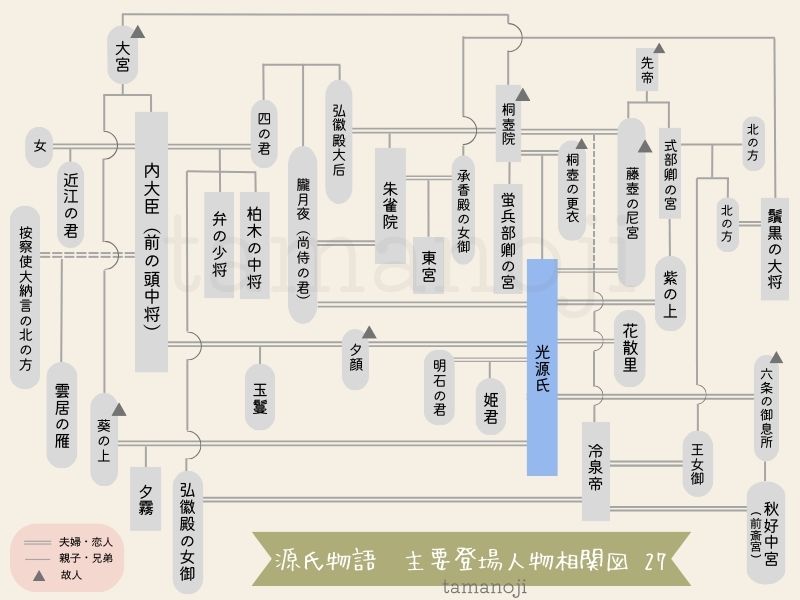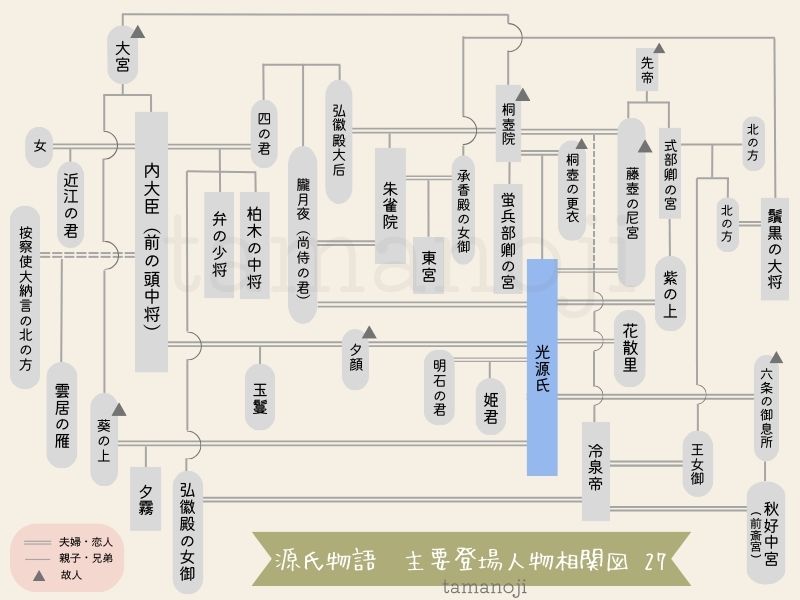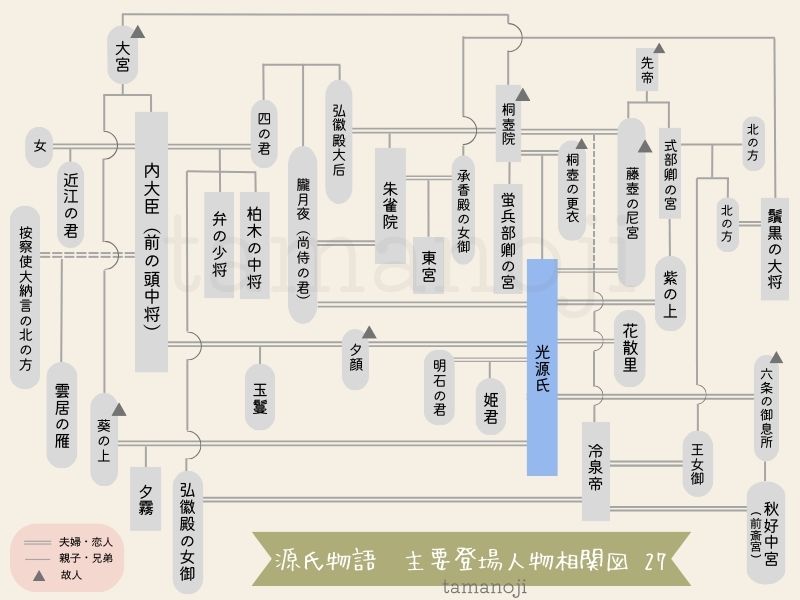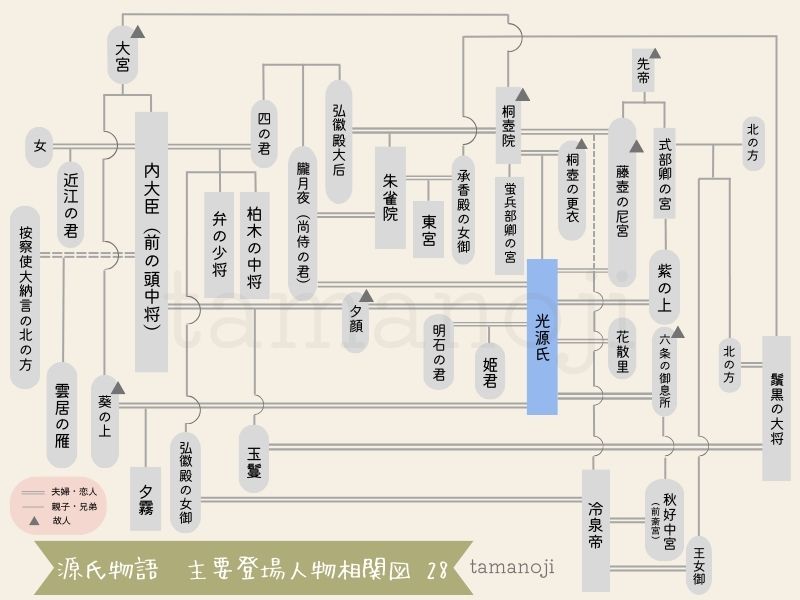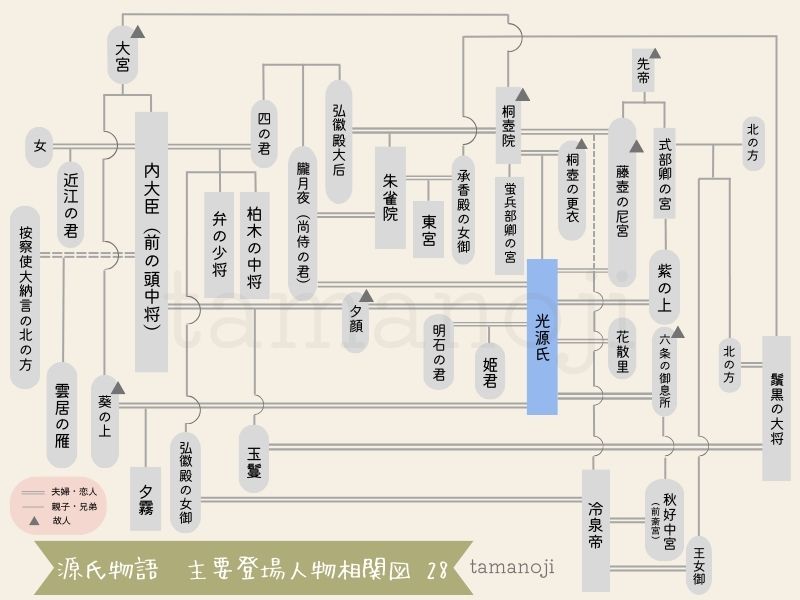プロモーションを含みます
2024年の大河ドラマは第63作『光る君へ』。時代は平安、主人公は紫式部。『光る君へ』では、藤原道長との出会いにより人生が大きく変わることとなる紫式部の人生が描かれています。
紫式部を演じるのは吉高由里子さん。藤原道長は柄本佑さんが演じます。
私は『源氏物語』を読み始めました。『源氏物語』は紫式部の唯一の物語作品。せっかくなので、『源氏物語』を読み進めるのと並行して、あらすじや縁のある地などをご紹介していこうと思います。これを機に『源氏物語』に興味を持っていただくことができたなら、とても嬉しいです。
※和歌を含め、本記事は文法にのっとっての正確な現代語訳ではありません。ご了承ください。
←本のマークの部分だけを読むと、さらに時間を短縮して読むことができます。
*****
▼巻ごとのあらすじを中心に、名場面や平安の暮らしとしきたりを解説。源氏物語が手軽に楽しくわかる入門書としておすすめの一冊!
リンク
*****
目次
第29帖 行幸(みゆき)

大原野への行幸
十二月に大原野への行幸(みゆき・ぎょうこう:帝の外出)があるというので、世間は大騒ぎ。六条院からも女君たちが見物に出かけます。
玉鬘も見物に行き、父である内大臣に注目していました。いかにも立派で美しく、男盛りではありましたが、誰よりも優れた臣下という印象でしかありません。
若い女房たちは、近衛の若い中将や少将などを「美しい」「素敵だ」と騒いでいますが、玉鬘が唯一心惹かれたのが冷泉帝でした。源氏の君と顔はそっくりですが、帝はより威厳があってとても立派に感じました。赤色の袍を身に着けて、端然と正面を向いたままじっとされているお姿は、他の誰とも比べようがないほど素晴らしいものでした。
蛍兵部卿の宮もいらっしゃいます。鬚黒の右大将も大層あでやかな衣を着て参列していますが、色黒でひげが濃い右大将のことを、玉鬘はとても好きにはなれません。
玉鬘は宮仕えをするか迷っていますが、「帝の寵愛を受けるかどうかはさておき、普通に仕えて帝にお目通り願うのであれば、楽しそうだ」と思いました。
 月耕『源氏五十四帖 廿九 御幸』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション
月耕『源氏五十四帖 廿九 御幸』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション
次の日、源氏の君は玉鬘に、「帝をご覧になって、宮仕えの件は決心されましたか」と文を送ります。玉鬘は「心の中を見透かされているようだわ」と思いますが、「あまりはっきりと見えませんでしたので」と返事をします。それでも源氏の君は、「決心してください」と宮仕えを勧めるのでした。
うちきらし朝ぐもりせし行幸にはさやかに空の光やは見し
“霧で朝曇りして雪も降っていた行幸でしたので はっきり帝の顔も見えませんでした”
玉鬘
あかねさす光は空に曇らぬをなどて行幸に目をきらしけむ
“日の光は曇りなく空にさしていましたのに なぜ雪に目を曇らせてしまったのですか”
源氏の君
「はっきりと顔が見えなかったから」と言い訳する玉鬘に、源氏の君は「帝は輝くばかりに美しかったはずですが、なぜきちんと見なかったのですか」と突っ込んだのでしょうね。
内大臣への告白
玉鬘はまだ裳着の儀(女性の成人式に当たる儀式)を済ませていなかったので、年が明けた二月に執り行おうと、源氏の君は必要な調度類などを揃えます。
また、「もし尚侍としての出仕が実現するのであれば、自分の娘のままでは不都合だな。これを機に、私から内大臣に打ち明けよう」と、源氏の君は腰結(腰のひもを結ぶ役)を内大臣にお願いしようと文をさし上げました。
しかし、大宮(内大臣の母・夕霧の祖母)が去年の冬から病がちなので都合が悪い、との返事がありました。確かに、夕霧もずっと大宮の看病に徹しているので、どうしたものかと考えます。
源氏の君は、「もし仮に大宮がお亡くなりになれば、玉鬘も喪に服すべきなのに、このままではそれもできない。それなら大宮が御存命のうちに打ち明けてしまおう」と思い、三条の宮にお見舞いへ行きました。
「腰結」とは
裳(下袴)を初めて身に着ける「裳着(もぎ)」は女子が成人するときに行う儀式。その儀式において、元服の加冠の役に相当する最も重要な役が、裳を着せる役である「腰結(こしゆい)」の役。一族の長や人徳のある人がその役に選ばれました。
源氏の君は、以前よりもますます光り輝いてこの世のものとは思えない美しさなので、久し振りにお会いすした大宮は気分の悪さも吹き飛んでしまい、起き上がっていらっしゃいました。
「夕霧が大げさに嘆いていましたので、とても心配していましたが、それほど悪くはないようで安心しました」と源氏の君が言うと、大宮は「もうあなたにお会いしてお話することもできないのかと、心細く思っておりました。夕霧が真心こめて世話をしてくれるので、今まで生き永らえています」と泣きながら声をふるわせて話します。

昔や今のことをあれこれ話した後、源氏の君は「実は内大臣に折り入ってお話がございまして…」と切り出しました。大宮は「まあ、私も『一旦噂が立ってしまったのだから、もう無理に引き裂かなくても』と言ったのですが、内大臣は昔から一旦決めたことは譲らない性分ですから」と、夕霧と雲居の雁のことだと勘違いしているので、源氏の君は改めて話し出します。
「実は、内大臣がお世話するべき人を、思い違いから私が引き取ってしまったのです。娘に年齢などを聞いているうちに、内大臣が引き取るべき娘であるとわかったので内大臣にお伝えしたいのですが、なかなかお会いできません。宮様から内大臣に話していただけませんか。」
大宮は内大臣に文を出し、「私が呼んだとばれないようにさりげなく来てくださいませんか。あなたにお話もあるようなので」と伝えます。
内大臣は「雲居の雁と夕霧のことだろうか。宮と源氏の君がどうしてもと言うなら、もう許してしまおう。」と考えながら、大宮の邸へと向かいました。

息子たちを大勢引き連れて入る内大臣の様子は、堂々として貫禄がありました。背丈もすらりと高く、程よく太っていて威厳があり、顔付きや歩き方も大臣らしいものでした。
一方、源氏の君の落ち着いた風格はたとえようもなく美しいものです。内大臣がいくら着飾ったとしても、比べようもないほど光り輝いています。
内大臣は、久し振りに源氏の君と会い、昔のことを思い出しています。離れていると些細なことにも競争心が生じますが、こうして面と向かって話すと昔のように心の隔てもなくなり、長年の積もる昔話に花を咲かせて、すっかり日が暮れていきました。
折を見て、源氏の君は玉鬘のことを話しました。内大臣は、
「あの頃から気になって探していたのです。今はこうしてあちこちにいた子供たちを集めて並べてみると可愛いと思いますし、行方知らずになってしまった子も自ずと思い出さずにはいられませんでした。」
と話しているうちに、あの若かりし頃、雨夜にいろいろと打ち明け話や女の品定めをしたことを思い出して、泣いたり笑ったりして、二人はすっかり打ち解けたのでした。
実はこの時、内大臣は源氏の君のことを少し疑っているんです。
「探して手に入れた娘に、源氏の君が手を出さないわけがない。娘のままでは他の女君と同列に扱えず、世間体もあるので、私に打ち明けたのではないか。」と。
それでも「例えそうだとしても、源氏の君に娘を差し出すことに何の不都合があるだろうか。とにかく源氏の君の考えに従うことにしよう」と思います。
一方で、「もし玉鬘を宮仕えさせて帝のそばに置くとなると、玉鬘の異母妹である弘徽殿の女御にとって良くないのではないのだろうか」など、あれこれと考えを巡らせているのでした。
裳着の儀

源氏の君は、急いで裳着の準備をします。内大臣に打ち明けた時の様子や儀式で心得るべきことを源氏の君から教えられた玉鬘は、その行き届いた心遣いに感謝し、父と会えることも嬉しく思っています。
そして源氏の君は夕霧にも本当のことを話します。
夕霧は「怪しいと思っていたら、そういうことか」と納得します。
あのつれない雲居の雁よりも、美しい玉鬘の方が思い出されて、全く気付かなかった自分の間抜けさを思い知ります。「雲居の雁がいながら他の女に思いを寄せるのは間違ったことだ」と思い返すところは、世にも稀な誠実さの表れなのでしょう。

裳着の日、大宮からお祝いの手紙が届き、源氏の君の女君からも次々に贈り物が届きます。二条の東の院にいる末摘花からも、本来なら遠慮すべきところなのに、古めかしい袴一式や小袿などが届きます。添えられていた歌もあいかわらずひどく、源氏の君はとても恥ずかしく思うのでした。
そして内大臣が御簾の中に入ります。一度は断った腰結を快く引き受け、涙を流しながら裳の腰紐を結び、
「言葉では言い尽くせないほど感謝しておりますが、今まで隠しておられたことへの恨みも申しあげないではいられません」と内大臣は言います。
すると源氏の君が、「誰も訪ねてくれないような憐れな身だったのですから仕方ないのですよ」と玉鬘をかばいます。「それはもっともなことだ」と思い、内大臣はそれ以上何も言わず出ていきました。

玉鬘に想いを寄せる人たちもたくさんお祝いに来ていました。内大臣が御簾の中に入ってしばらく出てこないので、皆どうしたのだろうと不思議に思っています。
内大臣の長男である柏木の中将や次男の弁の少将だけは、うすうす事情を知っていました。秘かに慕っていたので実の姉だとわかってつらいとも思うのですが、嬉しいとも思うのでした。
あの蛍兵部卿の宮は、「裳着を終えた今となっては、もうお断りになる理由がないのではないでしょうか」
と熱心に求婚しますが、源氏の君は「冷泉帝から尚侍にとご内意がありますので、他のお話はそれがどうなるか決まった後で、ということで」と言いました。
内大臣は、玉鬘が尚侍になるかもしれないので、弘徽殿の女御にはきちんと事情を説明しておきました。
困り者の近江の君
あの困り者の近江の君が、弘徽殿の女御・柏木の中将・弁の少将が揃っているところにやってきて、「父君が迎えた姫君は、卑しい生まれだそうですね」と無遠慮に言います。あまりに聞き苦しいので女御は黙っていますが、中将は「慎んだ方がいいですよ。」と言います。
すると近江の君は「尚侍になるそうではないですか。尚侍になりたいから私も女房たちが嫌がることも進んでやっているのに。」と怒って言いました。
それを聞きつけた内大臣は、陽気に笑って近江の君を呼び出します。
「尚侍のことだが、どうしてわたしに早く言ってくれなかったのですか。」と真面目くさって言うと、近江の君は嬉しく思って、「女御様がそれとなく伝えてくださるだろうと頼り切っていたのですが、他の方が尚侍になると聞いてがっかりしました。」と元気よく言います。
内大臣は笑いそうになるのをこらえて、「言ってくだされば、真っ先に奏上しましたのに。今からでも申し文を作りなさい。上手に詠んだ長歌があればうまくいくと思いますよ。」とからかうように言います。
すると近江の君は、「歌は下手でも何とかして作るので、申し文の方は大臣がお作りになって、わたしは言葉を添えるだけでいいのですが・・・」と両手をすり合わせて頼むのでした。御几帳の後ろで聞いている女房は、死にそうなほどおかしがっています。
内大臣は、「嫌なことがあった時は、近江の君を見ると何だか気が紛れるな」と言って、近江の君を笑い者にするのでした。
玉鬘のことで、源氏の君に「隠していたことを恨んでいるとあなたは言うけれど、あなたが悪いのですよ」と言われてむしゃくしゃしていた内大臣は、近江の君をからかうことによって、自分の心を慰めたのです。
*****
▼姫君はネコ、殿方はイヌのイラストで、物語の全体像を分かりやすく解説!当時の皇族・貴族の暮らし、風習、文化、信仰などについても詳しく紹介されています。
リンク
*****
第30帖 藤袴(ふじばかま)

夕霧の玉鬘への想い
玉鬘は尚侍として宮仕えすることを迷っています。
内大臣にも源氏の君にも勧められるのですが、「宮仕えして万が一にも帝のご寵愛を受けようものなら、秋好中宮にも弘徽殿の女御にも良くは思われないだろう。かといって、このまま六条院にいると源氏の君に言い寄られてしまう。内大臣は堂々と引き取ってくれそうもないし。」と、父である内大臣に会ってからは、源氏の君も遠慮しなくなってきたので、玉鬘は人知れず嘆くのでした。

玉鬘は、亡き大宮の喪に服するため、薄い鈍色(濃い灰色)の衣をまとっています。そこへ夕霧が、少し濃い鈍色の直衣姿で訪ねてきました。
実の姉弟ではありませんでしたが、今までどおり、几帳を添えて御簾越しに直接話します。夕霧は、源氏の君の使いで、帝からの仰せ事を伝えに来たのでした。
夕霧は、あの野分の朝に垣間見た玉鬘の顔が忘れられず、実の姉ではないことがわかった今となっては、恋心を募らせています。
「喪服を脱ぐ月になりましたね。父大臣が、十三日に賀茂の河原で禊をするようにとおっしゃっています。わたしもお供いたしますので」と夕霧が言うと、玉鬘は「私が喪に服している(大宮と縁がある)ことはあまり知られない方がいいのではないでしょうか。夕霧様とご一緒だと目立ってしまいます」と心配します。
夕霧は、「私もあなたも同じ宮様の孫なのですね。あなたが喪服を着ていなければ、信じられないところです」と言い、美しく咲いた藤袴の花を御簾の端から差し入れました。
そして、その藤袴を玉鬘が手に取った時、玉鬘の袖をさっとつかんで引いたのです。
同じ野の露にやつるる藤袴あはれはかけよかことばかりも
“私たちは同じ祖母の死を悲しみ 同じ藤色の喪服を着ているのです そんな縁があるのですから ほんの少しでも 私のことを想ってくれませんか”
夕霧
 フジバカマ
フジバカマ
「藤袴」は「藤衣(喪服)」を連想させます。また、藤袴は薄紫色の花で、平安時代、紫色は「縁」を連想させる色でした。夕霧は「あなたとは縁がある」という自分の歌に合わせて、藤袴を玉鬘に贈ったのです。
また、「女性の袖を引く」というのは、男性がその女性に好意があるという現れ。「夕霧様までもがそんなお気持ちを持っているなんて…」と玉鬘は困ってしまいます。そして返事をしました。
尋ぬるにはるけき野辺の露ならば薄紫やかことならまし
“血筋をたどって私とあなたの縁が薄いのであるなら この薄紫の花もお近づきになる口実になるのでしょうに”
玉鬘
つまり、「あなたとは兄弟同然で濃い縁があるので、薄い縁を表す薄紫の花(=藤袴)は私たちには関係のない花ですよね(これ以上お近づきになる口実にはならないでしょう)」と夕霧に伝えることで、夕霧の気持ちを退けたのでした。
夕霧は、「あなたが宮仕えなさることを知りながら、どうしても自分の心を抑えきれないのです。こんな私をせめて可哀そうだと心に留めてくださいませんか」と自分の気持ちを伝えますが、玉鬘は「気分が悪いので」と言って引っ込んでしまいました。「あんなこと、言うんじゃなかった」と夕霧は後悔するのでした。
 月耕『源氏五十四帖 三十 蘭』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション
月耕『源氏五十四帖 三十 蘭』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション
求婚者たちの困惑
夕霧は源氏の君を訪ね、玉鬘のことを伝えます。
「姫君は宮仕えをためらっていらっしゃいます。秋好中宮や弘徽殿の女御と肩を並べるのは難しいのですから。それに、姫君に夢中でいらっしゃる蛍兵部卿の宮は、姫君が宮仕えするとなりましたら、ご自分の気持ちが無視されたと思われるのではないでしょうか。」
それに源氏の君は答えます。
「私の一存では決められないことなのだよ。玉鬘は、蛍兵部卿の宮ともうまくやっていけるだろうし、宮仕えしたとしても、帝が望むとおりに立派に役目を務めるだろうけれど」
そして夕霧は源氏の君の本意が知りたくなり、
「内大臣が、『源氏の君は、玉鬘を女君たちと同様に扱えないため、とりあえず出仕させてから自分のものにしようとお考えなのでは』と思っていらっしゃるようです」と言うと、源氏の君は、「それは見当違いだよ。ずいぶんと気を回したものだね」と微笑みながら答えました。
しかし心の中では、「よく見抜いたものだ」と内大臣のことを気味悪く思っているのでした。
そして、玉鬘の宮仕えは十月に決まりました。冷泉帝はそれを待ち遠しく思っていました。
柏木の頭の中将は、思いを寄せていた玉鬘が実の姉だと知ったあと、内大臣の使いで玉鬘を訪ねた時に歌を交わしました。
妹背山深き道をば尋ねずて緒絶の橋に踏み迷ひける
“実の姉弟とは知らずに 遂げられない恋の道に踏み込み 文を送ってしまいました”
柏木
惑ひける道をば知らず妹背山たどたどしくぞ誰も踏み見し
“事情をご存じなかったとは知らずに 妙だと思いながらお手紙を拝見していました”
玉鬘

近衛府の長官の鬚黒の大将は、次官である柏木の頭の中将をいつも呼び寄せて、玉鬘と結婚したいと内大臣に伝えさせていました。鬚黒の大将は人柄もよく、東宮の後見となる人なので、何の問題もないだろうと内大臣は思っているのですが、「太政大臣(源氏の君)が姫君に宮仕えをさせるのは、それなりの理由があるのだ」と源氏の君に任せることにしました。
この鬚黒の大将は、東宮の生母である承香殿の女御の兄妹で、源氏の君・内大臣に次いで帝の信任が厚い人物です。北の方(妻)は式部卿の宮の長女で、紫の上の異母姉でしたが、大将はこの北の方とはうまくいっておらず別れようとしていました。
源氏の君は、北の方が紫の上の姉なので、鬚黒の大将と玉鬘の結婚はふさわしくないと考えています。しかし、鬚黒の大将は、「太政大臣の意向に沿っていなくても、実の親が反対していないのならば」と、玉鬘付きの弁のおもとという女房に仲を取り持つよう催促するのでした。

玉鬘は十月に宮仕えに出ることになっていたので、九月になると多くの恋文が届きました。いくつか紹介します♪
数ならば厭ひもせまし長月に命をかくるほどぞはかなき
“普通ならこの月を嫌がるものですが その九月を頼りに生きている私はなんと儚い身の上なのだろうか”
鬚黒の大将
玉鬘の出仕は十月。この月(九月)にはまだ出仕しないので、玉鬘をあきらめきれない鬚黒の大将は、この一か月に賭けようとしています。九月は結婚を避ける月なので、一般には忌み嫌われている月ですが、命を懸けて玉鬘に求婚しようとする大将にとっては、嫌な月ではなく、最後の頼みの月だったのです。たった1か月にすがる自分はなんと儚い身なのだろうかと嘆くのでした。
蛍兵部卿の宮からも歌が届きます。
朝日さす光を見ても玉笹の葉分けの霜を消たずもあらなむ
“たとえ帝のご寵愛を受けたとしても 玉笹の下葉についた霜のように儚いわたしの恋心を忘れないでください”
蛍兵部卿の宮
ひどくしおれて下が折れた笹の枝にくくりつけた手紙を、枝についた霜を落とさないように、使いの者が届けに来ました。使いの者でさえも、宮のような心遣いができるのです。そして歌には「せめてわたしのこの気持ちを知ってくださったなら、慰められようもございましょう」と添えてありました。
また、式部卿の宮の子息で、紫の上の異母兄弟にあたる左兵衛督も、玉鬘へ歌を届けます。
忘れなむと思ふもものの悲しきをいかさまにしていかさまにせむ
“あなたを忘れようと思うそのこと自体がとても悲しく いったいどうすればいいのでしょうか”
左兵衛督
「姫君が宮仕えされたら、こんなにすてきな方々があきらめてしまわなければならないのですね」と人々が噂する中、玉鬘は蛍兵部卿の宮へ返事を書きました。
心もて光に向かふ葵だに朝おく霜をおのれやは消つ
“自分の意志で光に向かう葵さえ 朝におりる霜を自分で消したりはしないのです”
玉鬘
つまり、「私は自分の意志で出仕するわけではないので、あなたのことを忘れたりはしません」と歌ったのです。玉鬘が蛍兵部卿の宮の恋心を受け止めているかのように詠んだので、ほんの一言の文でしたが、宮は嬉しく思うのでした。
玉蔓が自分で返歌したのは蛍兵部卿の宮だけ。玉鬘が「この人となら」と少しでも思えたのは、彼だけだったのかもしれませんね。
*****
▼訳・瀬戸内寂聴の「源氏物語」は、比較的わかりやすい文章で書かれているので、源氏物語を読破してみたい方におすすめ。全十巻からなる大作です。巻ごとの解説や、系図、語句解釈も付いています。
リンク
*****
第31帖 真木柱(まきばしら)

玉鬘の結婚
「こんなことが帝のお耳に入ったら恐れ多いので、しばらくは人に漏らさないように」と源氏の君は鬚黒の大将に忠告します。玉鬘は大将に打ち解けることもできず、なぜこんな宿命なのだろうとふさぎこんでいます。
大将は玉鬘を手に入れることができ、石山寺の本尊と弁のおもと(女房)を並べて拝みたいとさえ思っています。しかし、手引きをした弁のおもとは玉鬘に嫌われ、出仕できずに謹慎になっていました。
源氏の君は「不本意だが、こうなってしまっては仕方ない」と、婚礼の儀式などを立派に執り行います。
やがて帝もこのことを知り、自分とは縁がなかったのだろうと残念に思うのでした。
いきなり源氏の君のセリフから始まるこの帖。「いったい何が起きたの?」と読み進めてみると、どうも鬚黒の大将と玉鬘が一夜を共にしたようです。大将の一方的な思いのようですが…。
まさかまさかの急展開!一番ありえないと思っていた鬚黒の大将が玉鬘と結婚してしまいました…。
源氏の君は、鬚黒の大将がいない時に玉鬘の部屋へ行きました。玉鬘は、生真面目で平凡な夫と比べようもないほどすばらしい源氏の君を見て、思いもかけずあんな夫を迎えてしまった自分がとても恥ずかしくて、涙が止まらなくなります。
それを見て、源氏の君は、美しくて可憐な玉鬘を他人にやってしまうなんてと残念に思うのでした。
おりたちて汲みは見ねども渡り川 人の瀬とはた契らざりしを
“あなたと親しい仲にはならなかったけれど 三途の川を渡るときは他の男に背負わせるとまでは約束しませんでしたよ”
源氏の君
平安中期、「女性は死後、初めて契った男性に手を引かれて三途の川を渡る」という俗信がありました。また、『蜻蛉日記』では、「女性は初めて契った男性に背負われて三途の川を渡る」という意味の歌が詠まれているそうです。
みつせ川渡らぬさきにいかでなほ 涙の澪の泡と消えなむ
“三途の川を渡りきってしまう前に なんとかして私の涙の川に浮かぶ泡となって消えてしまいましょう”
玉鬘
玉鬘の歌を聞いた源氏の君は、「泡になって消えるなんて幼いことを言いますね。あの川は避けることのできない道だから、あなたの手の先だけでも引いて助けてさしあげましょう」 と微笑みました。
源氏の君は、「帝がまだ『出仕するように』とおっしゃっているので、やはり少しでも出仕するようにとり計らいましょう。鬚黒の大将があなたを邸に取り込んでしまうと、出仕もむずかしくなってしまいますからね。」と玉鬘に言います。玉鬘は、気恥ずかしい思いで聞きながら、ただ涙を流していました。
鬚黒の大将は、少しでも早く玉鬘を自分の邸に移したいと思っているのですが、源氏の君はすぐには許しそうもない様子です。

鬚黒の大将の北の方

鬚黒の大将は、玉鬘を迎えようと、自分の邸を修理するなど準備を急いでいました。
北の方が悩んで悲しんでいるのも気づかず、かわいがっていた子どもたちにも目を留めなくなりました。
北の方は、あの式部卿の宮(紫の上の父)がとても大事に育てたので、世間の評判も良くとても美しい方です。しかし、異常に執念深い物の怪に憑りつかれてからは正気を失うことが多々あり、とうの昔に夫婦仲も疎遠になっていました。それでも、正妻として他に並ぶ人もいないので、鬚黒の大将はこの方だけを大切にしていました。
ところが大将は玉鬘に心惹かれてしまったのです。北の方の父である式部卿の宮は、「若い姫君を迎える大将にすがりついているのは世間体も悪い」と、北の方を自分の邸に移そうと思っていますが、北の方は「夫に捨てられた身で実家に戻るなんて」と悩んでいるうちに気持ちがいっそう思い乱れて病気が悪くなり、すっかり寝込んでしまいました。

日が暮れ、大将は玉鬘に会いたくなって出かけようとすると、雪が降っていました。北の方が「あいにくの雪ですね。夜も更けましたよ」と行くのを勧めるように声を掛けます。「止めても無駄だ」と北の方は思っているのです。
大将が「大臣たちの手前、今、通うのをやめるわけにはいかないのだよ。どうか分かっておくれ。あなたがこうして普通でいる時は、あなたのことが愛おしいのだから」と話すと、北の方は「心が他にあるのにここにいてくださるよりも、よそにいても心から思ってくださるほうが嬉しいのです」と穏やかに言いました。
夫婦としてあまりうまくいっていないながらも、お互いに大切に思っていそうな感じはします。ただ、北の方だけに向いていた大将の気持ちが玉鬘にも行ってしまうことによって、少しずつすれ違ってしまったみたいですね。
雪が小降りになり、大将が出かけようとしたその時、北の方が急に香炉を取り、その香炉の灰を大将にさっと浴びせたのです。女房たちが防ぎようもない一瞬の出来事で、大将は呆然としています。
着替えようとしても、体中が灰だらけになっていて、出かけることができなくなってしまいました。あのもののけのせいだとわかっていても、大将は北の方のことが嫌でたまりません。
翌日、日が暮れるといつものように玉鬘のもとへ行き、ずっとそこに居続けるのでした。

姫君の手紙
北の方の父・式部卿の宮はこのことを聞き、「大将が娘をそんなにないがしろにしているのなら、もうそこにいる必要はない」と迎えを出したので、北の方もとうとうこの邸を出る決心をしました。
日も暮れて雪が降りそうな心細い空模様の夕べです。三人の子どもたちも北の方について行きます。大将にとてもかわいがられていた姫君は、出ていく前に大将に別れを告げたいと思いますが、日が暮れようとしているこんな時に、大将が玉鬘のところから戻ってくるわけがありません。
いつも自分が寄りかかっていた東面の柱のひび割れのすきまに手紙を押し込んで、邸を離れていったのでした。
今はとて宿かれぬとも馴れ来つる 真木の柱はわれを忘るな
“もうこれっきりだとこの家を去っても 長年馴れ親しんだ真木の柱は私を忘れないでね”
真木柱(鬚黒の大将の姫君)
馴れきとは思ひ出づとも何により 立ちとまるべき真木の柱ぞ
“慣れ親しんだ真木の柱が私たちを思い出してくれるとしても 私たちはどうしてここに留まれましょう”
北の方

北の方が実家に帰ったと聞いた鬚黒の大将は、世間体を気にして、式部卿の宮の邸を訪ねることにしました。大将は玉鬘に対して申し訳なさそうにするのですが、玉鬘はこういうごたごたを聞くにつけても自分の身が情けなく思えて、見向きもしません。
とりあえず自分の邸に戻った大将は、女房から真木柱(姫君)のことを聞き、真木柱が詠んだ歌を見て涙が止まらなくなります。そのまま式部卿の宮邸へ向かったのですが、北の方に会えるわけもありません。姫君にも会うことができず、幼い男君二人だけを連れて帰りました。
そして、自分の邸に二人を残して、また玉鬘のもとへと向かうのでした。
その後、大将は式部卿の宮邸へ手紙も送らず訪れもしなくなったので、式部卿の宮は大そうひどい仕打ちだと嘆いていました。
紫の上もこのことを聞いて、「私まで恨まれているのがつらいのです」と嘆いているので、源氏の君も困ったものだと思うのでした。
なぜ、紫の上は「自分は恨まれているはずだ」と思ったのでしょうか。
式部卿の宮は紫の上の父。しかし、源氏の君が須磨に行った時、世間体を気にして源氏の君を見放したのです。そのため、源氏の君は宮のことをあまりよく思っていなかったので、宮の娘が入内したときにも何も協力せず、梅壺の女御(秋好中宮)を中宮に推したので、宮の娘は中宮になれませんでした。
しかも「源氏の君が自分の愛人としていた(と噂されていた)玉鬘を大将に押し付けたから、娘が実家に戻ることになったのだ」と宮の北の方は思っていて、「きっと紫の上も協力しているに違いない」とも思っているのです。それを紫の上は見抜いていたのでしょう。
このようないろいろな騒ぎがあって、玉鬘はふさぎ込んでしまいました。大将はそれを気の毒に思い、気が晴れるのではと、参内させることにしました。
ただ、玉鬘がそのまま宮中に住みついてしまっては困るので、夜になったら退出するようにと言っていたのですが、源氏の君が「帝の許しが出てからにしなさい」と玉鬘を引き留めてしまいました。
そして、冷泉帝が玉鬘のところへお越しになりました。「私の気持ちをご存じだと思っていたのですが、結婚してしまったのですね」と帝は優しく言います。玉鬘はいたたまれない気持ちになり、顔を隠して返事をすることもできません。
などてかく灰あひがたき紫を心に深く思ひそめけむ
“どうしてこんなに一緒になりがたいあなたを 深く想うようになってしまったのだろう”
冷泉帝
大将は、帝が玉鬘に会いに行ったことを聞いて焦り、早く退出するように玉鬘に言います。父の内大臣も帝に口添えし、ようやく帝の許可を得て退出することになりました。
それを見計らって、大将は「風邪を引いてしまって自邸で静養しようと思うので、妻にも一緒に来てもらいます」と、そのまま玉鬘を邸に引き取ってしまいました。
源氏の君は「まさかあの真面目な大将がこんな強引になさるとは」と、とても悔しがります。源氏の君は、ついに玉鬘を奪われてしまったのでした。
十一月になり、玉鬘はかわいらしい男の子を産みました。鬚黒の大将はもちろん、父の内大臣もとても喜んでいます。
柏木の頭の中将は、今では玉鬘を姉として慕っており、
「帝はまだ皇子がいないことを嘆いていらっしゃる。産まれたこの子が帝の皇子だったなら、どんなによかっただろうに」と、身勝手なことを考えているのでした。
*****
▼大和和紀さんの漫画『あさきゆめみし』は読みごたえがある超大作。私は源氏物語を読む前に、あさきゆめみしを読破しました。「源氏物語の訳本を読んでみたけれど、文章がわかりにくくて挫折した」という、じっくりと源氏物語を読んでみたいという人にとてもおすすめです。
私は↓この「完全版」ではなく、文庫サイズのもの(全7巻)をBOOK・OFF(ブックオフ:古本)で買って揃えました♪
リンク
*****
石山寺*紫式部が『源氏物語』の着想を得た寺

石山寺とは
石山寺は滋賀県大津市にある真言宗の大本山の寺院。琵琶湖から流れ出る瀬田川の西岸に位置します。文学作品である『蜻蛉日記』や『更級日記』、『枕草子』にも登場するお寺で、『源氏物語』の作者・紫式部はここで物語の着想を得たと言われています。
また、紅葉の名所としても知られており、西国三十三所第13番札所です。
珪灰石(けいかいせき)と多宝塔

本堂に向かって上がってくると、目に入るのが珪灰石(けいかいせき)。大きくそびえるこの珪灰石は、天然記念物に指定されています。
この珪灰石の上方に見えるのが多宝塔。源頼朝が寄進により建立されたとされる日本最古の多宝塔で、国宝に指定されています。
本堂

滋賀県最古の木造建築。1078年に焼失し、1096年に再建されました。1952に国宝に指定されています。この階段を上ると・・・

「紫式部源氏の間」があります。
今を去る約千年の昔 寛弘元年八月十五夜 紫式部この部屋に参籠し前方の金勝山よりさし昇る中秋の名月が下の湖面に映える美しい景色に打たれ構想の趣くままに筆を採られたのが有名な「源氏物語」であります。それからこの部屋を「紫式部源氏の間」と申すようになったのであります
源氏の間 説明板より
また、石山寺では紫式部がデザインされた御朱印帳もあります。
 少し小さめ・蛇腹式・ビニールカバー付き
少し小さめ・蛇腹式・ビニールカバー付き
紫式部像

宇治の紫式部像は有名ですが、石山寺にも紫式部像があります。宇治の像よりも少しほっそりしてますね。坂道や階段をのぼってのぼってのぼって行ったところに、なんだかひっそりと寂しげにたたずんでいます。「紫式部像を見たい!」という方には、スニーカーで行くことをおすすめします。
大本山 石山寺
住所:滋賀県大津市石山寺1-1-1